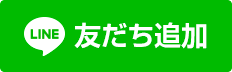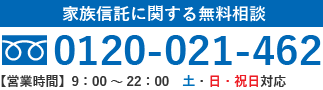今回は親が「認知症」になってしまった場合の財産管理について解説していきたいと思います。
「親が認知症になってしまったが、何をすればいいか分からない」
「財産管理はどうすればいいの?」等、様々な疑問を持たれると思います。
今回は親が「認知症」になってしまったときのためにすべきこと・財産管理のやり方等について説明していきますので上記のような疑問を持たれる方等の参考になれば幸いです。
目次
- 親が「認知症」になって財産管理でよくある問題
- 「認知症」になった親の口座が使えなくなる!?
- 契約や遺産分割協議が無効!?
- 詐欺や悪質商法の被害
- 親が「認知症」になった場合の財産管理の対策方法
- 家族信託で「認知症」対策
- 任意後見で「認知症」対策
- 成年後見で「認知症」対策
- 成年後見で「認知症」対策
- 『成年後見』の申立方法
- 誰が申し立てることができるの?
- 申立先はどこ
- 申立てに必要な費用
- 申立てに必要な書類
- 財産管理で気をつけるべきポイント
- お金や財布を取り上げない
- 悪徳商法や詐欺に気を付ける
- まとめ
親が「認知症」になって財産管理でよくある問題
親が「認知症」になってしまったら困ることを以下で紹介していきます。
「認知症」になった親の口座が使えなくなる!?
多くの金融機関では口座の名義人が「認知症」になった場合、口座が凍結します。
つまり口座からお金を引き出せなくなってしまいます。
上記のような状態になると「認知症」になった親の医療費や施設費などの支払いを立て替えることになります。医療費や施設費などは高額になるため、困ったことになります。
契約や遺産分割協議が無効!?
「認知症」等、意思能力がない方が法律行為をしたとしても無効となります。
例えば以下のような場合に困ったことになります。
| 事例
Aには配偶者のBと子のCがいます。Bは認知症になってしまいました。その後Aは亡くなりました。 |
この場合、Bは認知症であるため遺産分割協議ができません。遺産分割協議ができない場合、銀行の口座解約や不動産の名義変更などで手続きができないということになります。
詐欺や悪質商法の被害
「認知症」になると判断能力が低下するため詐欺や悪質商法の被害に遭うリスクが高くなります。さらに、「認知症」になると被害に遭ったとしてもその後の適切な対処ができないことになります。
親が「認知症」になった場合の財産管理の対策方法
「上記のような事態になることを防ぐためにはどうすればいいのでしょうか?」と思われる方は多いと思います。以下では親が「認知症」になってしまった場合の対策方法の種類について説明していきます。
家族信託で「認知症」対策
家族信託は、自分の老後等に備えて所有している不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理等を任せる方法です。
しかし家族信託は財産管理を任せたい人と財産管理をする人が契約をする必要があります。親が「認知症」になってしまった後に家族信託を利用しようとしても「認知症」の症状によっては上述したように契約が無効となる場合があり、家族信託を利用できない場合があります。家族信託について詳しくは他のブログ
(https://osaka-kazoku-shintaku.jp/archives/1667)を参考にしていただけると幸いです。
任意後見で「認知症」対策
任意後見とはご本人の判断能力が不十分な状態となる前に、本人が後見人を事前に決めておくという制度です。任意後見人に与える権限も本人で決めることが可能です。
例えば認知症になった時に備えて、後見人を決め、預貯金の財産管理や入院・施設の入所手続きをしてもらうという利用方法が考えられます。
任意後見の制度を利用するには任意後見契約書を作成する必要があります。任意後見契約を締結するには公正証書でしなければなりません。
そのため、「認知症」の症状によっては上述したように契約が無効となる場合があり、任意後見を利用できない場合があります。
任意後見について詳しくは他のブログ(https://osaka-kazoku-shintaku.jp/archives/1636)を参考にしていただけると幸いです。
成年後見で「認知症」対策
本人が「認知症」となり、判断能力を失ってしまった場合の唯一のとりうる方法です。法務省によると成年後見とは「本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度」としています。
任意後見と異なる点は任意後見では本人が後見人を事前に決め、任意後見人に与える権限も本人で決めることが可能ですが、成年後見は裁判所の判断次第となるため本人の希望どおりになるとは限りません。
『成年後見』の申立方法
今回は成年後見の申立方法について説明していきます。
以下は裁判所のホームページ
(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html)を要約したものですので詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
誰が申し立てることができるの?
以下の人が申し立てることができます。
| 本人(後見開始の審判を受ける方)
配偶者 四親等内の親族 未成年後見人 未成年後見監督人 保佐人 保佐監督人 補助人 補助監督人 検察官 (任意後見契約が登記されているときは,任意後見受任者,任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。) |
申立先はどこ
本人の住所地の家庭裁判所です。詳しくはこちらの裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html)をご覧ください。
申立てに必要な費用
申立費用は以下のとおりです。
| ・申立手数料 収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(裁判所により異なります。) ・登記手数料 収入印紙2600円分 ※精神状態により別途、鑑定費用がかかる場合があります。 |
申立てに必要な書類
申立てに必要な書類は以下のとおりです。詳しくはこちらの裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html)をご覧ください
| ・申立書
以下は標準的な申立添付書類であり、事例によっては異なる場合があります。
・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの) ・本人の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの) ・成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの) ※ 成年後見人等候補者が法人の場合には,当該法人の商業登記簿謄本(登記事項証明書) ・本人の診断書(発行から3か月以内のもの) ・本人情報シート写し ・本人の健康状態に関する資料 介護保険認定書,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,身体障害者手帳などの写し 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)
・本人の財産に関する資料 ・預貯金通帳写し,残高証明書など ・不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など ・ローン契約書写しなど ・本人の収支に関する資料 |
財産管理で気をつけるべきポイント
財産管理で気を付けるべきポイントを以下にまとめましたので参考にしていただけると幸いです。
お金や財布を取り上げない
「認知症」になった親が金銭管理をできないからと無理やりお金や財布を取り上げないようにしましょう。家族に対する不信感により、今後の資金管理にも影響を及ぼすことがあります。
悪徳商法や詐欺に気を付ける
悪質商法等の被害に遭ったらすぐに消費者生活センターや弁護士などの専門家に相談しましょう。また、「しばらく「認知症」の親に会っていなかったら未開封の商品が大量に・・・」という事態にならないためにも定期的に会いに行きましょう。
まとめ
以上が、親が「認知症」になってしまった場合の財産管理についてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。
| 親が「認知症」になってしまったら困ること | ・認知症になった親の口座が使えなくなる
・契約や遺産分割協議が無効 ・詐欺や悪質商法の被害 |
| 親が「認知症」になってしまった場合の対策方法として何がある? | ・家族信託
・任意後見 ※上記は「認知症」の症状によっては利用できない場合があります。 ・成年後見 |
| 成年後見の申立方法 | ・詳しくは裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html)をご覧ください |
| 財産管理で気を付けるべきポイント | ・お金や財布を取り上げない
・悪徳商法や詐欺に気を付ける |
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
「無料相談」のご予約は下記の「空き状況検索」からできます。是非ご活用ください。
| 相続サイト | |
| 所在地 |
|
| 問い合わせ |
|
| その他 |
|
著者情報
代表 柳本 良太

- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格